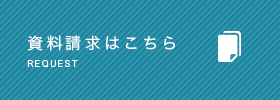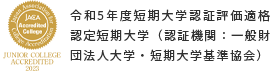国際こども教育学科DEPARTMENT OF ICO
教員紹介
教員紹介
間野 百子Momoko Mano
教授

- 職 位
- 教授
- 学 位
- 博士(子ども学)修士(教育学)
- 専門分野
- 教育学(社会教育学、教育社会学)、子ども学、世代間交流学
- 研究テーマ
- 幼児期における体験格差、課題を抱える子ども・若者支援
- 所属学会
- 日本教育学会、日本社会教育学会、日本乳幼児教育学会、日本世代間交流学会、日本更生保護学会、日本福祉教育・ボランティア学習学会
- 主な担当科目
- 保育・教職実践演習、保育内容特論、教育実習指導、サービス・ラーニング、英語で伝える日本文化、保育実習指導Ⅰ、キャリアデザイン、演習ゼミ
- 教育活動
- 学生との関りを通して、子ども・若者には無限の可能性があること、夢や希望に向けて努力を積み重ねていくことにより、自らの可能性を拓いていけることを伝えていきたいと考えています。子ども理解を保育者の立場で深めていく授業では、子ども一人ひとりに備わっている学ぶ力や可能性に重きを置いている理論や方法論について検討しています。
- 研究活動
- さまざまな課題を抱えている子ども・若者の支援に地域住民が関わる活動を通して、支援する立場の人も学びを深めていくという、地域社会循環型の相互支援・学習活動の役割について探求してきました。現在は、体験活動の質・量の格差が幼少期から拡大し始めることを踏まえて、幼児教育の現場において実施されている格差縮小に向けての活動や保育者による支援のあり方についての実証研究に取り組んでいます。
- 社会的活動
- 特定非営利活動法人「日本世代間交流協会」理事(2007年6月~2021年6月)
文部科学省国立教育政策研究所「生涯学習の学習需要の実態とその長期的変化に関する調査研究」調査員(2012年4月~2015年3月まで)
小田原市放課後児童クラブ運営事業者選択委員会委員・副委員長(2020年4月~2020年7月)
特定非営利活動法人「日本世代間交流協会」監事(2021年6月~現在に至る)
小田原市放課後児童クラブ運営事業者選択委員会委員・副委員長(2023年4月~7月)
日本世代間交流学会紀要編集委員(2024年4月~現在に至る) - 主要業績
- 【著書】
『世代間交流効果―人間発達と共生社会づくりの視点から』(共)2009, 草野篤子・金田利子・間野百子・柿沼幸雄編著,三学出版,「序章 (前文pp.1-7)」;「終章 (pp.235-241)」(共), 担当:第15章「青少年の発達支援における『メンタリング』活動」(pp.205-220)
『世代間交流学の創造ー無縁社会から多世代間交流型社会の実現のために』(共)2010, 草野篤子・柿沼幸雄・金田利子・藤原佳典・間野百子編著, あけび書房,「序章 (pp.14-20)」;「終章 (pp.238-242)」(共), 担当:第Ⅰ部第3章「世代間の相互学習・相互支援の視点から」(pp.49-59)
『教育老年学と高齢者学習』(共)2012, 堀薫夫編著, 学文社,担当:第6章「アメリカにおける高齢者のセルフ・ヘルプ・グループの展開:孫を養育する祖父 母たちの活動を事例として」(pp.170-186)
『世代間交流の理論と実践1:人を結び、未来を拓く世代間交流』(共)2014, 草野篤子他編著, 三学出版, 担当:第4章「非行少年の更生支援における民間ボランティアの役割―BBS運動に焦点をあてて」(pp.41-53)
『保育学生のための基礎学力演習ー教養と国語力を伸ばす』(共)2021, 馬見塚昭久・大浦賢治編著, 中央法規出版, 担当項目:「教育の原理―語源からひもとく」「すべての子どもに教育をーペスタロッチの実践より」「遊ぶことは学ぶことー子ども固有の『遊ぶ』権利」「子どもが主人公の遊び場・学び場―冒険遊び場・プレーパーク」「子どもの個性・想像力を育む教育実践―レッジョ・エミリア・アプローチ」「広島のマザー・テレサ『ばっちゃん』―子どもたちに心の居場所を!」「文字の読み・書きができる喜びー夜間中学における学び」「教育を第一に!―マララさんの願い」
『保育・教職実践演習ー実践力のある保育者を目指して』(共)2023, 野津直樹・宮川萬寿美編, 萌文書林, 担当:第2章4節「ラーニング・ストーリーによる子ども理解の深まり」(pp.64-82) - 【学術論文】
「世代間統合施設の今日的意義と課題―米国の展開をとおして」(単)2005, 『生涯学 習・社会教育学研究』第30号, 東京大学大学院教育学研究科生涯教育計画講座社会教育研究室, pp.11- 20
“Role of Self-help Activities in Lifelong Learning: An Examination of the Grief & Loss Programs in the U.S.”(単)2007,『都留文科大学紀要』第66集, 都留文科大学, pp.139-151
“Role of Intergenerational Mentoring for Supporting Youth Development: An Examination of the ‘Across Ages’ Programs in the U.S.” (単)2007, Educational Studies in Japan, International Yearbook, Japanese Educational Research Association, No.2(『教育学研究』英語版, 第2号, 日本教育学会, pp.83-94)
「成人教育におけるセルフ・ヘルプ活動の役割―米国の『祖父母の会』に着目して」(単)2009, 『アメリカ教育学会紀要』第20号, pp.58-69
「米国における祖父母と孫の世代間家族の現状と課題―孫を養育する祖父母支援に焦点をあてて」(単)2012,『日本世代間交流学会誌』第2号, pp.9-17
「孫の養育者としての祖父母の役割―アメリカの『一世代スキップした家族』に着目して」(単)2013, winter『季刊家庭経済研究』 No.97, 家庭経済研究所,pp.42-49
「ボランティア活動が若者に及ぼす影響―教育理論と教育効果の視点から」(単)2017, 『小田原短期大学研究紀要』第47号, pp.21-26 「課題を抱える少年支援ボランティアは活動をどのように体験するかー―活動開始前の非行問題との接点や関心の程度とBBS会『ともだち活動』における学びに焦点を当てて」(単)2019, 『日本福祉教育・ボランティア学習学会研究紀要』 第32号, pp.17-28
「少年支援ボランティアの長期継続を通した援助成果の認識―BBS会『ともだち活動』体験者の継時的変化に焦点をあてて」(単)2019,『更生保護学研究』 日本更生保護学会, 第15号, pp.3-12
「課題を抱える少年とBBS(Big Brothers and Sisters) 会ボランティア援助者の相互交流プロセスー複線径路等性アプローチ(TEA Trajectory Equifinality Approach) による分析」(単)2021,『小田原短期大学研究紀要』第51号, pp.33-44
「子どもの主体性をはぐくむ活動―教育原理と教育実践を通しての考察」(単)2022, 『小田原短期大学研究紀要』第52号, pp.33-44
「課題を抱える少年支援におけるボランティア援助者の役割―長期継続者の学びに着目して」(単) 2023, 『小田原短期大学研究紀要』第53号, pp.55-71
「子ども理解におけるラーニング・ストーリーの特徴と保育者志望学生の学び」(単) 2024,『小田原短期大学研究紀要』第54号, pp.9-20
「幼児期における体験活動の意義と格差解消に向けた取り組みー神奈川県内の幼稚園を対象とした質問紙調査ともとに」(共)2025,『小田原短期大学研究紀要』第55号, pp.45-66 - 【学会発表】
世代を結ぶ―共生型社会の構築と世代間交流の可能性」(共)2005, 「世代を結ぶ―共生型社会の構築と世代間交流の可能性」日本社会福祉学会第53回研究大会、シンポジスト(東北福祉大学)
「世代間交流学の創造に向けて―理論と実践の統合」(共)2010, 日本世代間交流学会第1回研究大会(芦屋大学)
「米国における世代間メンタリング活動の展開―困難を抱える子ども・若者の発達支援」(単)2010, アメリカ教育学会第22回研究大会(芝浦工業大学)
「世代間交流プログラムの従来型と発展型の検討-祖父母と孫の世代間家族を事例として」(単) 2012, 日本世代間交流学会第3回全国大会(名古屋芸術大学)
「異世代間の関係を構築する―子育て支援につなげるための理論の検討」(共)2013, 日本発達心理学会第24回大会ラウンドテーブル(明治学院大学)
「非行少年の更生支援における民間ボランティアの役割―世代間メンタリングの機能に着目して」(単)2014, 日本世代間交流学会第4回研究大会(東京都健康長寿医療センター)
大会企画セッション「ともだち活動の現状と課題について―BBS運動を最も特徴づける活動を考える」(共)2016, 日本更生保護学会第4回大会(慶応義塾大学)
「幼稚園における自然体験活動の意義と課題」(共) 2024, 日本乳幼児教育学会第 34回大会(アイーナ:いわて県民情報交流センター)
- 【著書】
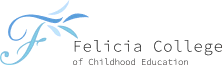


 資料請求
資料請求